今回紹介する本は長友佑都選手はじめ多くのアスリートの個人トレーナーとして活躍する木場克己氏の「続ける技術、続けさせる技術」。
ちなみに ” 木場 ” と書いて ” こば ” と読みます。
木場克己氏は、小学2年生より父親から強制されて柔道をはじめ、中学卒業までの間に九州大会の団体戦優勝、個人戦では県大会準優勝するなど輝かしい成績を残しています。
高校進学時には柔道の強豪校から声がかかるものの、レスリング部に入部。ここでも九州大会優勝、インターハイ団体戦3位という好成績を収めています。
その後は、地元の体育大学に進学して「オリンピック選手」 ⇒ 「体育の先生」という青写真を描いていましたが、試合中の転倒で腰椎圧迫骨折というレスリング選手にとって致命的なケガをしてしまいました。
目指していたものが失われる瞬間って、普通の人であれば真っ暗になるでしょうね。ほんと何があるか分からないですが、木場氏は不思議と穏やかな気持ちになっていたと言います。
それから何をしようか考えていたところ、体の仕組みや故障のメカニズムを体系的に学び、施術の技術を習得したいと思うようになり、治療家・スポーツトレーナーの道を歩むことを決心します。
大学時代にヘルニアと腰椎分離症を患い、プロを諦めようとしていた長友選手に出会う。
長友選手は高校時代から腰痛に悩まされていて、大学に進学してからはアスリートとして致命傷となるヘルニア、腰椎分離症を患いプロの道も断念することも考えていました。
そんな中、当時のFC東京のGK・土肥洋一選手が
「木場さんというトレーナーがいるから、プロを諦める前に一度会ってみたらどうか」
と木場氏を紹介してくれたことがきっかけで長友選手の人生も大きく変わっていきます。
長友選手は木場氏の指導を忠実にこなし、継続していきました。
簡単なストレッチから徐々に負荷の高いトレーニングを取り入れていくとヘルニアによる痛みもなくなり、プロとして必要な身体を作り上げることに成功しました。
腰痛が解消したという話はよく聞きますが、ヘルニアの痛みが消えたというのはあまり聞かないですよね。すごいですね。。。
実は私も腰痛&ヘルニアなので、長友選手の行ってきたストレッチを真似してみようと、さっそく長友佑都選手の「体幹トレーニング20」という本を購入してみました。まだ読めていないですが、これから開く予定です。
「体幹トレーニング20」の内容は
「おなかを凹ませたい」
「キック力をつけたい」
「腰痛を解消したい」
「投げる力をつけたい」
他多数
など自分にも息子にも良さそうなストレッチ法があるので、試してみようと思います。
↓ ↓ ↓ 腰痛やヘルニアでお困りの方もぜひ参考にしてみてください。

木場克己氏が柔道を続けられた理由
「続ける技術、続けさせる技術」は、主に木場氏の経験をもとに、いかにモチベーションを下げずに、目標(ゴール)を達成するかが書かれていて大変勉強になりました。
” 続ける技術、続けさせる技術 ” を読み進めていくと、
「父親から強制されて柔道をはじめた」
というくだりが強く印象づけられました。
というのも、
息子のサッカーも私がスクールに参加させたことからスタートしているからなのです。(^^;)
木場氏は、父親に逆らえず始めた柔道を小学2年生から中学3年生まで打ち込んでいたとありました。途中、練習に行きたくない、やめたいと何度も何度も思ったそうです。
「柔道は自分の意思で選択したものではなく、父親から与えられたもの」
「高校でレスリングを始めたのも、自分がやりたいというよりも厳格な父親のもとから離れたいという思いから」
心の底から柔道を楽しんでいたわけではないのですが、結果を出すことで父親も母親も喜んでくれて、子どもながらにやりがいになっていたとありました。
子どもって親の顔色を見てますからね。
なんとなく分かる気がします。
木場氏が「スポーツトレーナー」となり感じていることは、最後は本人の意思や気づきが欠かせないということ。
「与えられたものでは伸びないし、そもそも継続のモチベーションも生まれません。自分がやりたいという強い意志を持つことこそ、継続の第一歩であり、こうした思いが強いメンタルの土台となるのです」
何をするにも、最終的にはやはり「本人の意思や気づき」が大切ということですね。
木場氏は
「厳格な父親に強制されて柔道をはじめた」
と述べていますが、それでも親の喜びがモチベーションとなって継続することができたとありました。
親の喜ぶ姿というのも「継続させる技術」のひとつとして大切なのかもしれませんね。
子どもの習い事の開始理由は各家庭それぞれですが、まず親も子供の習い事、日々の出来事に関心を持ちながら、一緒に喜んでみたり、タイミングをみて背中を押してあげることが大切なのかなぁと思いました。
息子も4年生になって自分から自主トレをするようになり、以前よりも積極的なプレーが見られるようになりました。息子の成長を感じています。
これからもっと ” 気づき ” が増えていけば、ますます上手くなっていくと思います。
親にやらされているのではなく、
「好きだからがんばっている」
「高い目標に向かって自分の強い意志で継続してる」
と思えるよう親として出来ることを考えながら接していこうと思います。
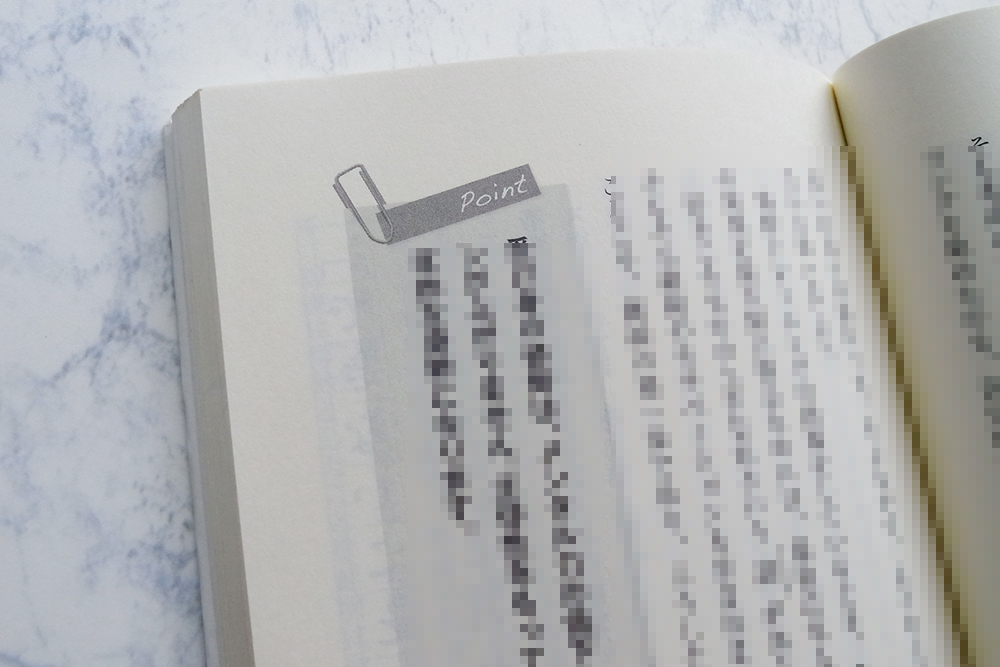
↑ 本文には「Point」が記されています。忙しい方は、ここを読むだけでも勉強になりますよ~。
子どもを正しいと思う方向に導くには「強制」も必要な時がありますが、アプローチの仕方を変えてあげることで「本人の意思や気づき」につながるかもしれません。
ヒントがたくさん書いてありますので、ぜひお手にとってお父さん、お母さんも挑戦してみてくださいね♪

読んで学べる面白いサッカー選手の本
光輝く表舞台ばかりではなくサッカーの裏側、選手の少年時代などどれも魅力あふれる面白い本ばかり。おすすめのものばかりです!
\ サッカー選手を目指す子ども必読! /
\ サッカーの裏側が知れる♪ /
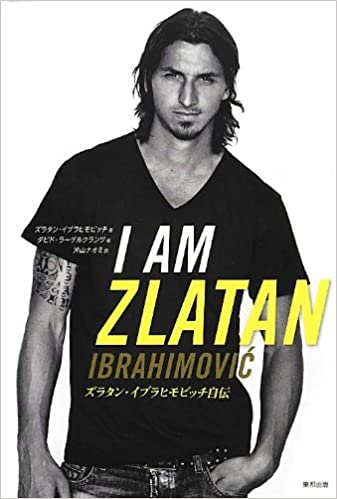
I AM ZLATAN ズラタン・イブラヒモビッチ自伝/イブラヒモビッチ
価格:¥1,980
出版社:東邦出版
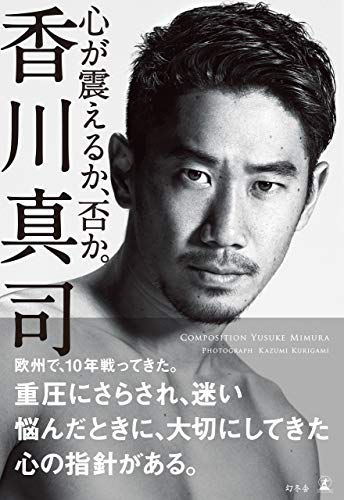
心が震えるか、否か。
価格:¥1.760
出版社:幻冬舎
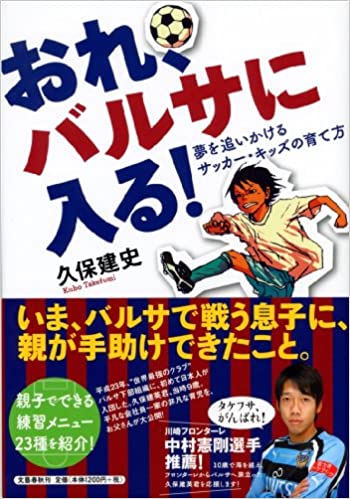
おれ、バルサに入る
価格:¥3,466~(中古品のみ)
出版社:文藝春秋
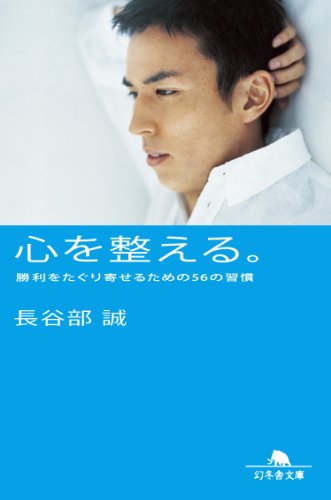
価格:¥715
出版社:幻冬舎文庫
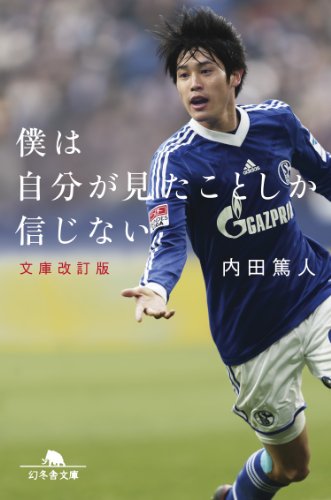
価格:¥796
出版社:幻冬舎文庫
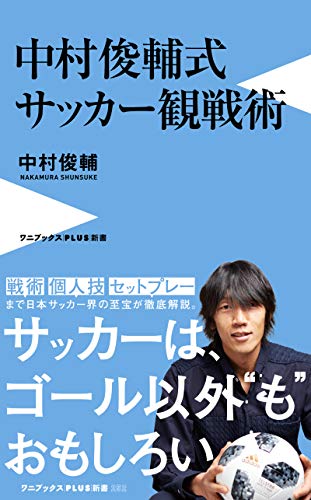
価格:¥968
出版社:ワニブックスPLUS新書




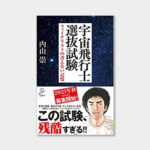


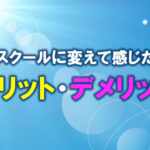

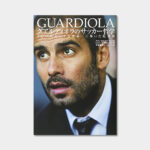

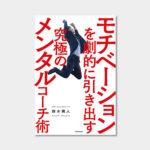
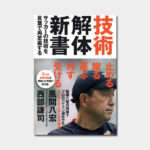
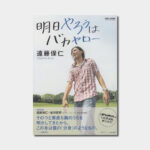
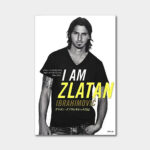
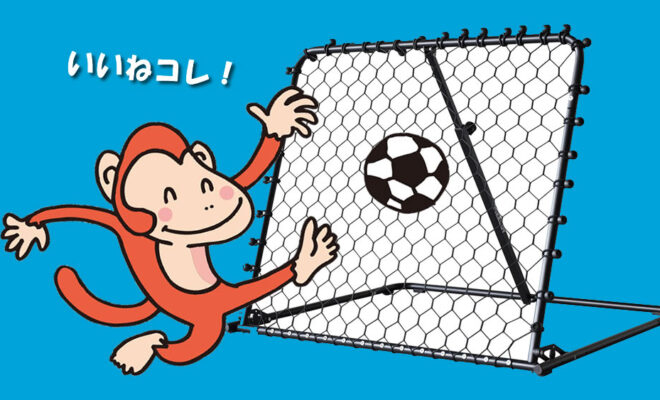









この記事へのコメントはありません。